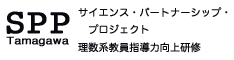
|
平成19年度 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(SPP)
|
|||||||
| 整理番号 | 講A学3102 | ||||||
|
日時
|
2007年9月10日、13日
|
||||||
| テーマ | 植物の進化と光合成色素 | ||||||
|
場所
|
玉川学園サイテックセンター(9/10, 13)
|
||||||
|
講師
|
井上 和仁 教授(神奈川大学 理学部 生物科学科)
|
||||||
|
参加生徒数
|
高校1年生 4クラス
|
||||||
|
概要
|
(9/10)
高等部1年若草組・霧島組(41名、43名:2クラス)を対象とした。 まず始めに、光合成のメカニズム、光合成色素の役割、光合成色素と植物の進化に関する講義を行った。 その後、様々な光合成生物から抽出した光合成色素を薄層クロマトグラフィーで分離した。実験に用いた光合成生物は光合成細菌(紅色細菌、緑色硫黄細菌)、ラン藻類(シアノバクテリア)、紅藻類(アサクサノリ)、褐藻類(ワカメ、ヒジキ)、緑藻類(アオサ)と種子植物(ホウレンソウ)である。授業時間の都合により生徒はホウレンソウからの色素の抽出だけを行い、他の光合成生物の色素は予めTAが神奈川大学で抽出しておいたものを使用した。これらの色素抽出液を幅広のクロマトシートに数種類スポットし、同時に展開させることによりそれぞれの光合成生物の色素を比較しやすくした。分離された色素の様子や色調、移動距離(Rf値)から光合成生物に含まれていた光合成色素を同定し、その結果を用いて植物の進化の過程を考察した。またクロマトグラフィーの原理について学び、なぜ色素によって移動距離が異なるのかを考察した。 実験の指導はTAが行ったが、指導の合間に生徒から実験に関する質問や大学生活に関する質問などを受けて、生徒と交流を深めていた。 (9/13) 高等部1年雲仙組・飛鳥組(42名×2クラス)を対象とした。9月10日(月)に行った活動と同様の内容を実施したが、前回の生徒の反応をもとにして、より分かりやすくなるように講義内容や実験手順を一部改良した。 |
||||||
|
写真・
資料等 |
|
||||||


